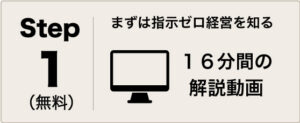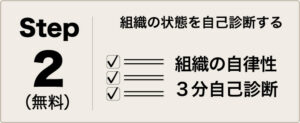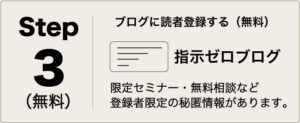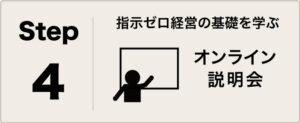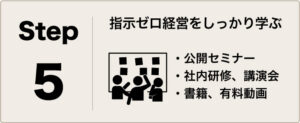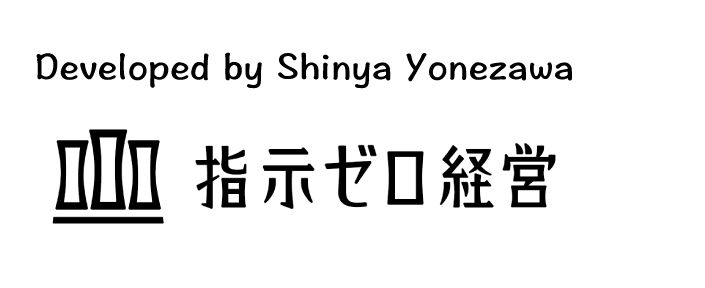賃上げの新潮流「第三の賃上げ」は企業を救うか?
時々、賃上げに関する記事を書きますが、もはや賃上げは「ムード」というよりも「圧力」という様相を呈しているように感じています。
政府が目標とする7.2%の賃上げを続けられると答えた中小企業はわずか1%にとどまっています。
そんな中「第三の賃上げ」で対応する企業が増えているという報道を目にしました。
第三の賃上げとは、定休昇給でもベースアップでもなく、福利厚生を充実させることで、社員の負担を減らそうというものです。
報道では、会社が用意した昼食のお弁当を100円で食べることができたり、奨学金を企業が代理返済したり、中にはマッサージが無料で受けられる企業までありました。
報道では、満面の笑みを浮かべる社員さんの姿が映っていましたが、僕は、率直に「この笑顔はいつまで続くのだろうか?」と思いました。
というのも、こうした福利厚生はあっという間に「あって当たり前」になり、より多くを要求するようになるからです。
もちろん、無いよりはマシですが、危険な側面があることを忘れてはいけないと思います。
アーノルド・トインビーという歴史家がいるのですが、彼は、著書「歴史の研究」で社会が衰退する最大の要因は「自ら考え決める」ことをしない人が増えることだと指摘しています。
このことは社会だけではなく企業にも当てはまります。経営者であれば経験的に理解できるのではないでしょうか。
先日、規則をなくしてダメになった学校のことを記事に書きました。
「なぜ「自由」は崩壊したのか?…自由と好き勝手の履き違えが生んだ顛末」
ダメになった要因は「子どもたちは、大人が用意した自由という名のプールで遊んでいただけで、自分で考え自由を獲得したわけではない」ということでした。
第三の賃上げは、社員の生活を守るという点で素晴らしい取り組みですが、一方で、危険性がはらんでいることも自覚する必要があります。
どうすれば「第三の賃上げ」は上手に運用することができるでしょうか。
そのヒントは、まさにトインビーの論にあります。
つまり会社が一方的に福利厚生を与えるのではなく、社員にも参画してもらい一緒に考えることです。
例えば、昼食の補助を出すなら、昼食のメニューを自分たちで考えるということです。
ちなみに、僕が経営してきた新聞店では、福利厚生はすべて社員が考えてくれました。
さらに素晴らしい取り組みをしている企業もあります。
先日、「指示ゼロ経営説明会」という勉強会を行い、ゲストに「クリーロ企業文化研究所」の大沼恭子代表(特定社会保険労務士)をお招きしました。
同研究所では、研修参加や書籍購入に対し、会社が費用を負担するという形で第三の賃上げを実施しています。
これを聞くと「会社都合ではないか?」という人がいますが、そんなことはありません。
なぜならば、社員さんが学ぶことを望んでおり、会社が補助してくれなくても自腹を切って自己投資をするからです。
どうしてそんな社員さんがいるのかというと、同研究所のビジョンや思想に賛同し、成長意欲を持った人を採用しているからです。
もちろん、学習補助もすぐに「あって当たり前」になります。しかし「もっと多く」が組織発展に繋がるものであれば意味合いは変わります。
第三の賃上げは、昨今の賃上げ圧力から回避するために、今後社会に広がると思いますが、その功罪を理解して取り入れることが大切だと考えています。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。