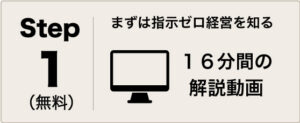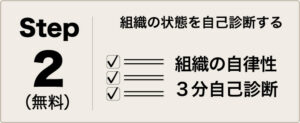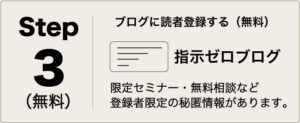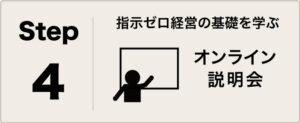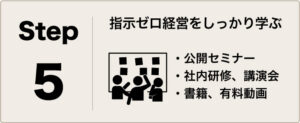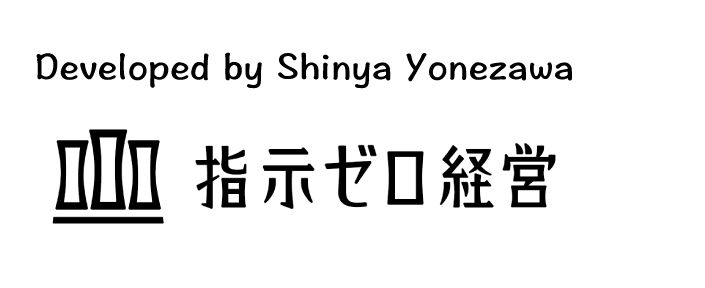リーダーの「部下の話を聴けない」はこう治す
人は、他人の話を聞いても、その内容の5%ほどしか学習できないと言います。
対し、自分が他者に話した時、特に、他者に教えた時は、内容の90%を学習すると言われています。
1on1の成長対話に注目が集まっている1つの理由がここにあると思います。
僕自身を振り返っても、社員が最も成長した時期と、僕が最も話を聴いた時期は合致しています。
朝、出社すると決まって応接室でブログを書くのですが、ドアは開けっ放しにしておきます。すると、出社した社員が「ちょっといいですか?」と入ってきます。
「こんなことを考えた」「こんな成果を出した」「失敗したが、次はこうしてみる」といった自慢話を聴くのが習慣でした。
人材育成の王道は「聴く」ということですが、これがなかなか難しい。
面談で、最初のうちは部下の話を聞いていたが、気づくと立場が逆転していたという経験はないでしょうか?
あるいは会議で、気づくとリーダーの独演になっていたりとか。
なぜ、リーダーは部下の話を聴けないのでしょうか?
「聴けずに喋ってしまう」ということですが、なぜ、喋ってしまうのでしょうか?
背景に「自分の賢さを誇示したい」「部下よりも有能だと思わせたい」「部下を従わせたい」「余計なことを言わせない」という「裏の欲求」がある可能性があります。
そうしないと自分を失うような気がして怖くなるのです。
「自分はそんなことはない」と思っていても、「裏の欲求」を自覚していない可能性を疑うべきです。
僕自身も、社員の話を聴けるようになったのは30代後半になってからで、それまでは、僕が一方的に喋ることが多かった。
「有能さを誇示したい」という自己顕示欲に取り憑かれマウントしてしまうのです。そういう時は大抵、社員の話を遮り、自分が持つ知識を披露したり、「俺も昔は…」といった武勇伝を語ったりしていました。
今になって思うと、聴けずに喋っている時は、ほぼ100%、裏の欲求に支配されていたと思います。
「裏の欲求」の根底には「思い込み」があります。
「リーダーは社内で一番賢くあるべきだ」とか「部下にナメられたらおしまい」という、勝手な思い込みです。
僕の場合、父の影響で、このような思い込みを持つようになったと考えています。父は夕飯を食べながらそんな話をする事が多く、聞くうちに刷り込まれたのだと思います。
思い込みから解放されたキッカケは、尊敬する先輩の、社員の話をじっくりと聴く姿を見たことでした。
本当に嫉妬するくらいカッコよかった。
自分もカッコいいリーダーになりたいと思い、試しに、社員の話に耳を傾けてみました。
すると、マウントできない恐れなど杞憂であることが分かりましたし、ナメられるどころか支持を集めるようになりました。
何よりも社員がイキイキし始めました。僕が聴くことで、こんな素敵な表情になるんだと思ったのです。
社員よりも、有能なリーダーよりも、社員が持つ僕よりも有能な部分を引き出せるリーダーの方が何倍もカッコいいと思えるようになりました。
「聴く」ということに限らず、人は何かしらの思い込みを持っています。
解放の鍵は、自分自身も気づかず、心の底に横たわっていると思います。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。