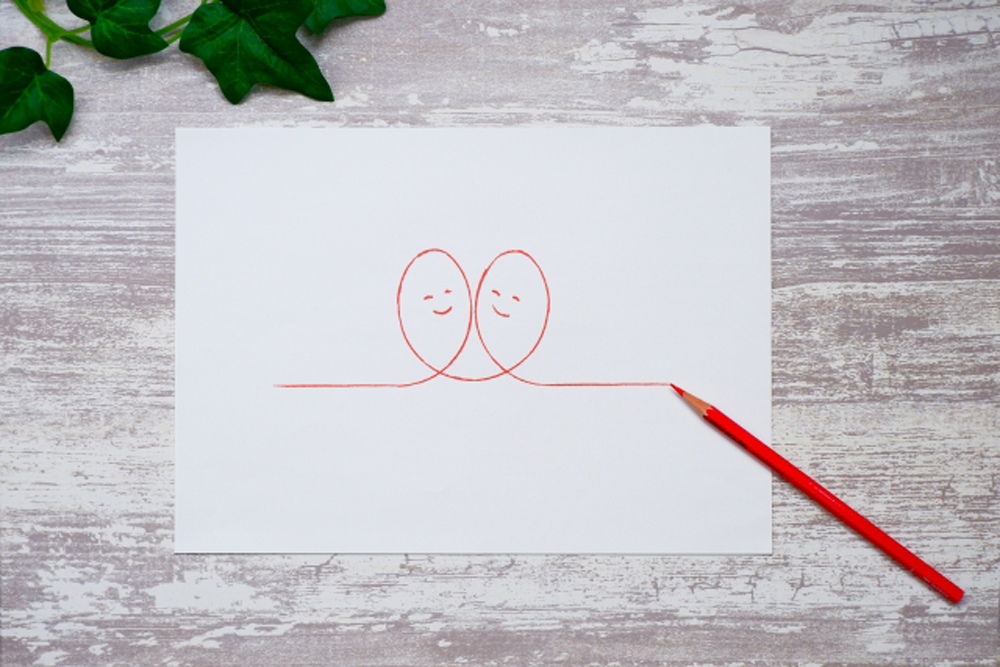対立を「建設的な対話」に変える。対話を決裂させない4つのポイント
リーダーは時として、話し合いの途中で決裂する可能性のある、ナーバスな対話をしなければならないことがあります。
僕も、解雇通達を覚悟して場に挑むような深刻な対話を何度も経験しています。
中には「深刻になってしまった」案件もあります。
どういうことかと言うと、対話を怠ったことで認識にズレが生じ、気づけば溝が広がっていたというケースです。
対話は筋トレと同じで、やらないと億劫になって、さらにやらなくなるんですよね。
数年前のことですが、そんな状態に陥った2人の対話の場に立ち会いました。
深刻な対話をする際には、当事者だけで話をせずに、司会者とオブザーバーを入れた方が上手くいきます。オブザーバーは話し合うテーマに応じた専門的な知見を持った人が適任です。
その時は、当事者をよく知る方が司会を行い、僕以外にもう1人のオブザーバーが立ち会い、合計5人で進めました。
その時に学んだ、ナーバスな対話を成功させるコツをシェアしますね。
.
❚ 席の配置は横並び
恋人と食事をする際、交際期間が長く、気を遣わない仲であれば対面が良いが、出会ったばかりでぎこちない場合は並んで座るのが良いという話を聞いたことがあります。
その時、当事者の2人には隣同士で座ってもらいました。

物理的な配置はメンタルに影響を与えます。正面に座ると「がっぷり四つ」の戦闘モードに入りやすいのに対し、横に並ぶと「同じ未来を目指す同志」という意識になりやすいのです。
実際にやってみて、できれば丸テーブルの方が話しやすくなるのでは?と思いました。
ちなみに、僕は「ミーティングで出た意見は付箋に書きましょう」と推奨しますが、これも同じ理由です。付箋に書いてホワイトボードに貼り出すと、みんなが付箋を見ながら対話をするからです。
.
❚ 司会者を通じ対話をする
次に司会の役割について。
司会は「初期設定」を行うところから対話を始めます。
初期設定とは「双方とも会社を良くしようと思っている」という確認です。両者とも会社を良くしようと思っているが、そのやり方で対立しているのです。初期設定により同志の関係であるという認識をセットするのです。
その日、僕はメンターの様子を見て、司会は自分の考えを述べず「壁」の役割に徹することが大切だということに気付きました。
当事者だけで対話ができればよいのですが、それが難しい場合は、司会を介し対話のキャッチボールを行うとやりやすくなります。

この構図で対話すると冷静に発言ができます。すぐに互いの考えが共有されるでしょう。
.
❚ オブザーバーの役割
オブザーバーは、対話の最中は発言はしません。
ある程度、対司会を通じた対話が進んだら、司会から「ではここでオブザーバーの意見や所感を聞きましょう」と伝えてもらい、一方的に所感を述べます。
僕がオブザーバーをやって思ったことは、具体的なアイデアは述べず、客観的な事実と事例を伝えることが大切だということです。
オブザーバーが伝え終わったら第2ラウンドのスタートです。
いや、表現が良くないですね。「ラウンド」というと闘いみたいですね…
.
❚ 結論を急がない
対話は「急がば回れ」に基づきます。結論が出なくても、互いの精神的な距離が縮まれば御の字です。もっと言えば、互いの考えが共有できただけでも大きな前進と捉えるべきだと思います。
というわけで、僕の体験を共有しました。
今、必要がなくても、リーダーはいつか深刻な対話をしなければならない場面に直面すると思います。
その時のために参考にしていただければ幸いです。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を!読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
▷セミナー、イベント、社内研修のお知らせ
■指示ゼロ経営マスタープログラム12期(2025年7月4日開講 全5回コース)
・自発的に共創するチームワークの条件
・短時間で豊かなアイデアを出す会議の進め方
・全員参加のプロジェクトの組み立て方
・自律型組織特有の部下との接し方
・自発的、継続的にPDCAを回すための仕組み
自分たちで課題を見つけ協働で解決する組織の絶対条件を学びます。
■社内研修のご依頼はこちら
みんなで学び一気に指示ゼロ経営の文化を創る。
現在「社内研修」を2社、「研修から伴走までの完全パッケージ」は1社受け付けております
■講演会を開催したい方
所要時間90分。経営計画発表会や新年決起大会の後に!
・自発的に働く意義と愉しさが体感できる。
・事例9連発!「自分たちにもできる」と行動意欲が高まる。