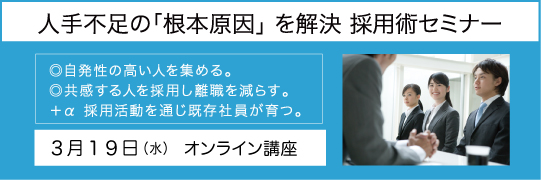リーダーは40歳で生まれ変わる
僕は30代の頃、出張に出ると、頻繁に社員から携帯電話が鳴りました。
その多くが指示を仰ぐ電話なのですが、それにテキパキと答える自分をカッコいいと思ったものです。
同時に、社員に頼られていることが気持ちよかったのも事実です。
しかし、これでは経営がおかしくなるのは自明のことです。
その理由は2つ。
1、社員が育たない。
2、僕が正解を示し続けることは不可能。
特に2が深刻です。
経験者なら分かると思いますが、40歳をすぎると、体力も思考力も判断力もガクッと落ちるものです。生物学的には、加齢による変化やホルモンバランスの変化などで、心身ともにさまざまな変化が現れる時期だそうです。
加え、過去の経験から「こういうもんだ」という固定観念ができます。固定観念の呪縛と判断力の低下というダブルパンチをくらうのです。
人間の能力には、「流動的知能」と「結晶的知能」の2つの側面があります。
流動的知能…状況の変化に合わせテキパキと思考、判断したり暗記をする能力
結晶的知能…経験から物事の原則、法則などを習得し実践に活かす能力
前者は20歳ころをピークに衰え、40歳には限界に達すると言われています。
以上のことを踏まえると、40歳を過ぎたころからマネジメントスタイルを変える必要があることが分かります。
つまり、テキパキと指示を出すのではなく「テキパキと自分で判断し行動できる部下を育てる」という方針転換です。
方針転換ができずに突き進むことは、流動的知能が盛んな若者からその機会を奪う&流動的知能が衰えた人間がそれをやるという、リーダーと部下、双方の強みを殺すことになります。
もう1つの弊害は、常日頃から指示を受けることに慣れた部下は、上司が変な指示を出しても、それに異論を唱えなくなることです。
何も言えないまま地獄にまっしぐらという悲劇が起きる可能性があります。
航空機事故の調査統計によると、航空事故は、副操縦士が機長が操縦桿を握っている時よりも、機長が握っている時の方が多く発生すると言います。
その理由は、パイロットの世界は、非常に上下関係の規律が厳しいので、機長の操縦に対し、副操縦士が物申すのは心理的な抵抗があり、組織で仕事をするメリット(多様性)が消されてしまうからです。
逆に、副操縦士が操縦している時は、機長のチェックの目が入りますので、様々なリスクを回避できるということです。
リーダーの中には、自分よりもテキパキと仕事をする部下の登場に対し、自分が敗北したような感覚にとらわれる人がいますが、決して敗北はありません。
サナギが蝶に変容するように、マネジメントスタイルを変える時が来たということです。
勝負すべきは部下ではなく自分自身なのです。
.
※「記事が面白かった」という方は、是非「読者登録」を。読者優先セミナーや無料相談など、登録者限定の秘匿情報が届きます。
採用術セミナーを3月19日(水)に行います。
✓自発性の高い人材がたくさん集まる
✓面接時の情熱とヤル気が入社後も続く
✓先輩社員が新人の教育に関心を持ち共に育つ
1年に2回だけの開催です。
↓詳細はこちらをチェックしてください。